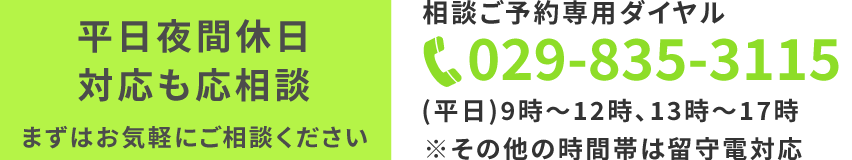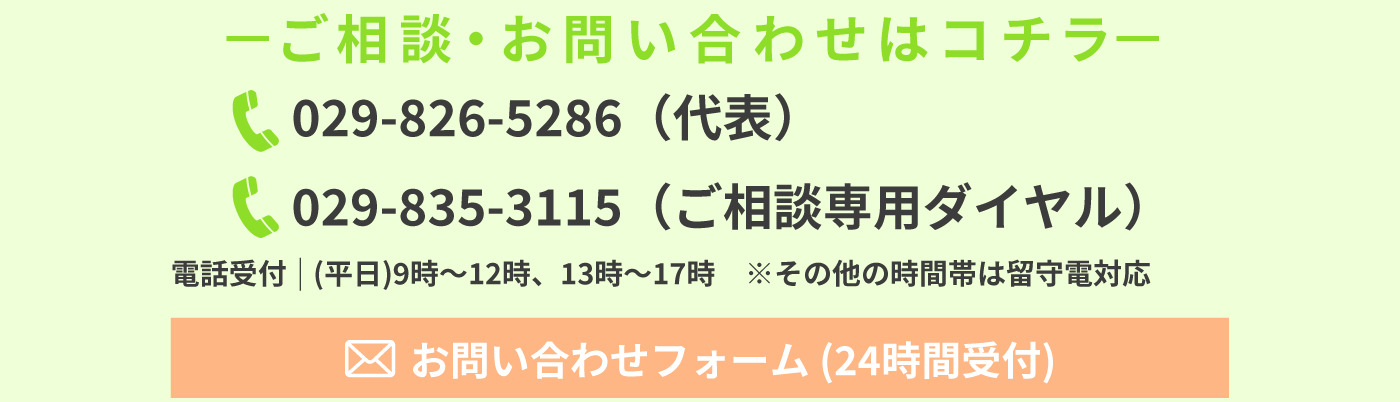Author Archive
全国倒産処理弁護士ネットワーク第36回関東地区研修会(静岡)に参加してきました。
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第65回関東地区研修会(静岡)に参加してきました。静岡県静岡市の静岡音楽館AOIにおいて、7月1日に行われました。
冒頭講演として、静岡地方裁判所民事第二部、部総括判事から静岡地方裁判所における倒産事件の状況が述べられました。時代を反映して倒産事件における個人情報の取扱いの説明も行われました。
また、今回の研修会はパネルディスカッションが中心に行われました。
「企業再生支援への取り組み~静岡銀行~」
「企業再生支援への取り組み~静岡キャピタル~」
「管財人から見た法人破産申し立てに関する諸問題」
以上のような三つのテーマです。
「管財人から見た法人破産申し立てに関する諸問題」では、我々の業務に直接かかわるところでもあり、いつもと同様に深く突っ込んだ議論がなされ、とても参考になります。
企業再生支援への取り組みをテーマにしたパネルディスカッションもコーディネーターやパネリストの皆様がとても魅力があったためか、とても興味深く勉強をすることができました。
そして、静岡県が企業再生支援に対してとても先端を行くお国柄を感じることができました。
懇親会では、焼酎のお茶割をいただきました。お茶の香りが強くとてもおいしくいただきました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続②「相続分はどのくらい?」
弁護士の若林です。
相続2回目は「相続分はどのくらい?」です。
第1回では磯野家を題材に「誰が相続人になるか」を説明しました。
波平さんの相続人は、舟さん、サザエさん、カツオくん、そしてワカメちゃんの4名でした。
では、各相続人の相続分はどのくらいになるのでしょう?
民法では相続人の順位に応じて相続分が定められています(法定相続分)。これを磯野家にあてはめてみましょう。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号に定めるところによる。
1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
(中略)
4号 子、直系尊属、又は兄弟姉妹が数人ある時は、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、(略)。
条文に従うと、妻(配偶者)である舟さんの相続分は2分の1となります。
そして、子であるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの3人は2分の1を平等に分けることになりますから、相続分は6分の1ずつとなります。
ちなみに、サザエさんが波平さんよりも先に亡くなっていた場合にはタラちゃんが相続人になります(代襲相続)。
この場合のタラちゃんの相続分は「サザエさんの相続分」、つまり6分の1です。
もっとも、相続人の全員で話し合い合意ができれば法定相続分と異なる相続分で分けることもできます。
例えば、舟さんが一人で相続財産の全部を相続することも、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの合意があれば可能なわけです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
法定相続情報証明制度について
弁護士の髙田知己です。
平成29年6月2日に参加した八翔会の勉強会で平成29年5月29日からスタートした法定相続情報証明制度についての案内がありました。
いままで相続に関する手続きをする場合、戸籍書類一式の束を銀行や登記所に使いまわして行わなければなりませんでした。しかし、この新しい制度を使うと、このような面倒が軽減されます。全国の登記所(法務局)において法定相続情報一覧図を作成し、これの写しの発行を受けることにより、この戸籍書類一式の束に変えることができるとのことです。この写しは必要な通数発行していただけ、しかもこの制度は無料とのことです。
裁判所での使用については、現在のところ正式な発表はないようですが、利用可能な方向での運用を期待したいところです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
第9回八翔会に参加しました。
弁護士の髙田知己です。
平成29年6月2日金曜日に第9回の八翔会に参加しました。八翔会は、コンパス・ロイヤーズ会計事務所(茨城県水戸市中央2丁目4-20ミトセンタービル2階)の代表税理士である井野武士先生が中心となって開かれている、士業限定の勉強会・懇親会です。おおむね3か月に一度くらい開催されている活気のある会です。第9回の勉強会は、午後2時30分から午後5時まで水戸生涯学習センター(茨城県水戸市三の丸1丁目5-38)3階中講座室にて行われました。
勉強会は、各士業が持ち回りで講師を担当します。今回は司法書士の先生方が担当です。勉強会は2部構成でした。第1部は信託について主に民事信託の構造や活用例までを伊藤拓也先生(司法書士 茨城さくら事務所)が担当されました。具体例なども交えてたいへんわかりやすい講義でした。
第2部は商業登記について法人の役員の任期や法人設立登記と許認可の関係について川又晋先生(水戸市中央2丁目5番8号第二くわばらビル2F)が担当されました。とても難しい分野だと感じますが、そこを感じさせないとても丁寧な講義を受けることができました。
懇親会は水戸市内の焼肉料理屋で開催されました。ここは各種士業の方々の忌憚のないご意見やご教示がいただける席です。楽しくかつためになる素晴らしい夜となりました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
「弁護士への依頼について」
弁護士の小沼です。
今回は,弁護士に相談や依頼をする手順についてご説明します。
1 弁護士へのアプローチ
日々の生活において法律トラブルが発生した場合には,弁護士に相談することが考えられます。弁護士へのアプローチ方法としては,①ホームページ等で法律事務所を探す,②弁護士会や市役所の法律相談を利用する,③法テラスで弁護士を紹介してもらう,などがあります。事前予約なしに訪れると,弁護士の都合がつかない場合がありますので,電話等で予め相談予約をすることが一般的です。
2 法律相談
法律事務所ごとに「相談料」の金額は異なります。当事務所の相談料は30分ごとに5000円(税込み5400円)となっておりますが,比較的多くの事務所で採用されている金額かと思われます。法テラスの制度を利用した無料相談等も実施しておりますので,お電話でご確認いただければ幸いです。法律相談のみで終了した場合,弁護士への依頼には至らず,費用も相談料のみとなります。
3 弁護士への依頼
法律相談を経たうえで,弁護士に依頼する場合,委任契約を締結することになります。弁護士に依頼する場合には,「着手金」「報酬金」「実費」がかかることが通常です(交通事故による損害賠償請求や過払金の回収等を依頼する場合には,「着手金」なしの「報酬金」のみという場合もあります。)。
「着手金」とは弁護士に依頼する場合にかかる費用のことで,依頼の成否にかかわらず発生します。「報酬金」は依頼が終了したときにかかる費用で,獲得した経済的利益に応じて発生します。「実費」は郵便切手代や印紙代などに使われた金額となります。
「着手金」「報酬金」「実費」等の弁護士費用については,契約前に説明がありますので,疑問を解消したうえで契約するようにしてください。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
まだまだある過払い金
弁護士の大和田です。
過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。
過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。
ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。
初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士高田知己が平成29年4月20日の読売新聞茨城版に掲載されました。
弁護士高田知己が平成29年4月20日の読売新聞茨城版に掲載されました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続①「相続人は誰?」
弁護士の若林です
相続の第1回目は「相続人は誰?」です。
相続が発生したら亡くなった方が残してくれた財産をどのように受け継ぐかを相続人みんなで決めなければなりませんね。
そもそも、誰が相続人になるのでしょう。
誰が相続人になるのかは法律でちゃんと定められています。法律から該当する部分を抜粋すると次のとおりです。
民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。
民法889条1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間ではその近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
民法890条
被相続人の配偶者は常に相続人となる。
文章だと今一つピンときませんね。
ここは国民的アイドル家族「サザエさん」でおなじみ「磯野家」に登場していただきましょう。
平成29年4月1日、大変残念なことに磯野波平氏が亡くなりました。
民法の規定からすると、波平氏の相続人は、波平さんの「配偶者」である舟さん、波平さんの「子」であるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの4名となります。
ところで、サザエさんは、磯野家に同居はしていますが、マスオさんと結婚してフグタ姓になっていますよね。
この場合も波平さんの相続人になるのでしょうか。
実際、相談者の方から「嫁に行った娘は相続人ではないですよね?」という質問を受けることがよくあります。
結婚して苗字が変わったとしても、サザエさんが波平さんの「子」であることには変わりありません。
ですので、「フグタ」姓になっていてもサザエさんも相続人となります。
磯野家では波平さんの「子」が健在なので、波平さんのご両親や兄弟姉妹が相続人となることはありません。
さて、波平さんよりも先にサザエさんがなくなっていたらどうなるのでしょう?
この場合も民法に規定があります。
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
つまり、サザエさんが波平さんより先に亡くなっていた場合は、サザエさんの「子」であるタラちゃんが相続人となります。
ちなみに、マスオさんは婿養子ではないため相続人ではありませんが、仮にマスオさんが波平さんの養子になっていたとすると、法律上「子」という立場になりますので、マスオさんも相続人となります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会に参加しました。
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会(高崎)に参加してきました。場所は、群馬県高崎市のホテルメトロポリタン高崎で、3月11日に行われました。。
冒頭講演として、前橋地方裁判所民事第二部判事補から前橋地方裁判所における倒産事件状況が述べられ、倒産事件における個人情報の取扱いや管財事件処理に関する前橋地裁における留意点などが挙げられていました。。
また、「行為者不在による企業の休廃業・解散を防ぐために」というテーマで公益財団法人群馬県産業支援機構群馬県事業引継ぎ支援センターの統括責任者から基調講演がありました。せっかく事業として維持できる組織であっても後継者が不在であることから、事業が休業や廃業となり、従業員の雇用が失われるなどの結果を回避しようとする手段が述べられました。大変興味深く茨城県における同様の活動などにも興味がわくものでした。
さらに倒産処理に関わる弁護士の職業倫理について、基調講演とパネルディスカッションが行われました。通常のパネルディスカッションでは他業種の話は出ないのですが、今回は公認会計士、税理士、中小企業診断士の参加をいただき弁護士と他業種を比較するといった視点から行われました。新鮮でもあり、新しいことにも気が付かされました。そして、あらためて弁護士の職業倫理の難しさを確認することになるものでした。
帰りには地元の方からお勧めいただいた、焼きまんじゅうを買って帰りました。大変おいしかったです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
月刊新聞モルゲンに弁護士高田知己の記事が掲載されました。
高田知己法律事務所です。
月刊新聞モルゲン(発行 株式会社 遊行社)2017年3月号に、当事務所代表弁護士高田知己の記事が掲載されました。月刊新聞モルゲンは、生徒会担当教諭、司書教諭を通して生徒に配布する、先生と生徒が、共有する読書を柱とした、人間の生き方を考える新聞です。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。