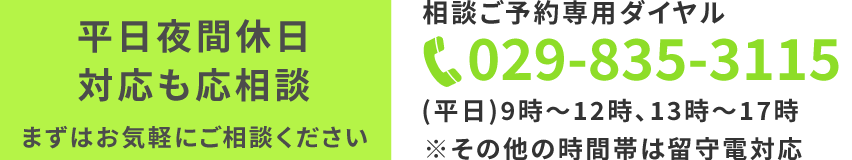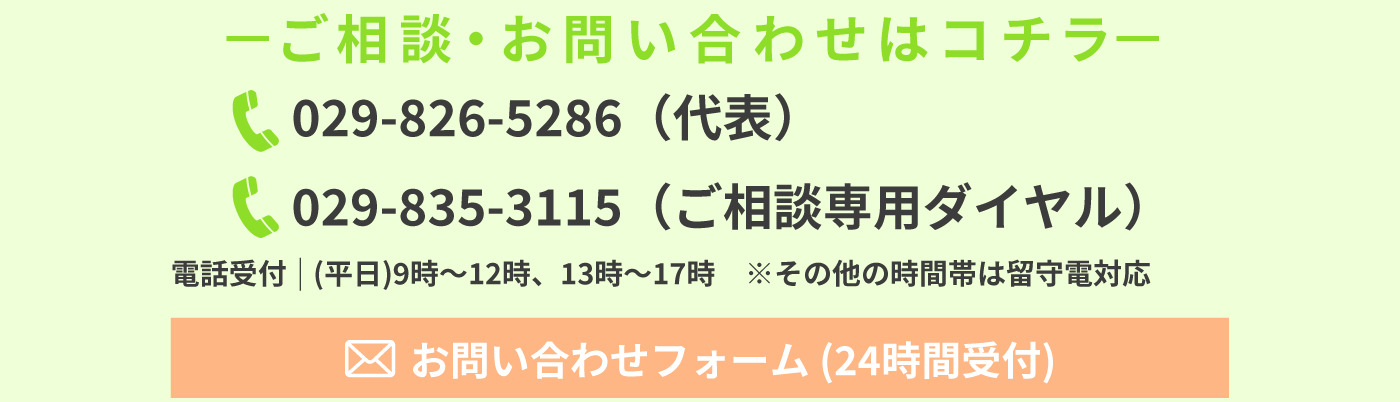弁護士の若林です。
今回は、相続の効力等に関する見直しについて説明します。
例えば、父親Aが亡くなり、相続人が長男Xと次男Yの2人であったとします。
Aの相続財産としては自宅不動産しかなく、かつ、Aは生前「自宅は長男Xに相続させる」との遺言書を作成していました。
Xが遺言書に基づいて自宅不動産の登記を自分名義に変更する前に、Yが法定相続分で登記手続きをしてしまい、その後第三者Sに自分の持ち分(1/2)を譲渡、登記をしてしまったとします。
つまり、本来Xの単独所有として登記されるべきところが、XとSが2分の1ずつ共有する内容で登記されている状態です。
この場合、改正前は、Xは登記を備えたSに対して、自宅不動産の所有権(全部)を主張することができました。
他方、Aが遺言書を作成しておらず、XとYが話し合い、自宅不動産をXが単独で相続する遺産分割協議をしていた場合で、その後YがSに持ち分(1/2)を譲渡、移転登記してしまった場合はどうでしょうか。
この場合、改正前は、Xは登記を備えていないため、YからSに対して自宅不動産の所有権(全部)を主張することができませんでした。
このように、法改正前、Xが登記を備えたSに対して所有権(全部)を主張できるかどうかは、AのXに相続させる旨の遺言の有無によって変わります。
ですが、通常、第三者は亡くなった人がどのような内容の遺言書を残していたのかを知ることは困難です。
それなのに、遺言の有無・内容によって権利関係が変わってしまうのは、第三者の利益を害することになりますし、登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれもあります。
そこで、改正法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとしました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。