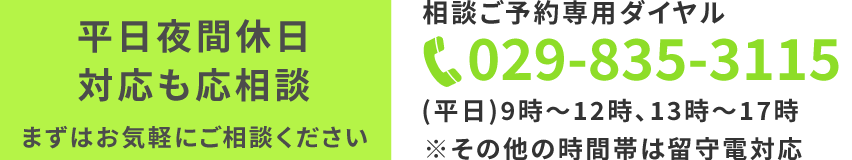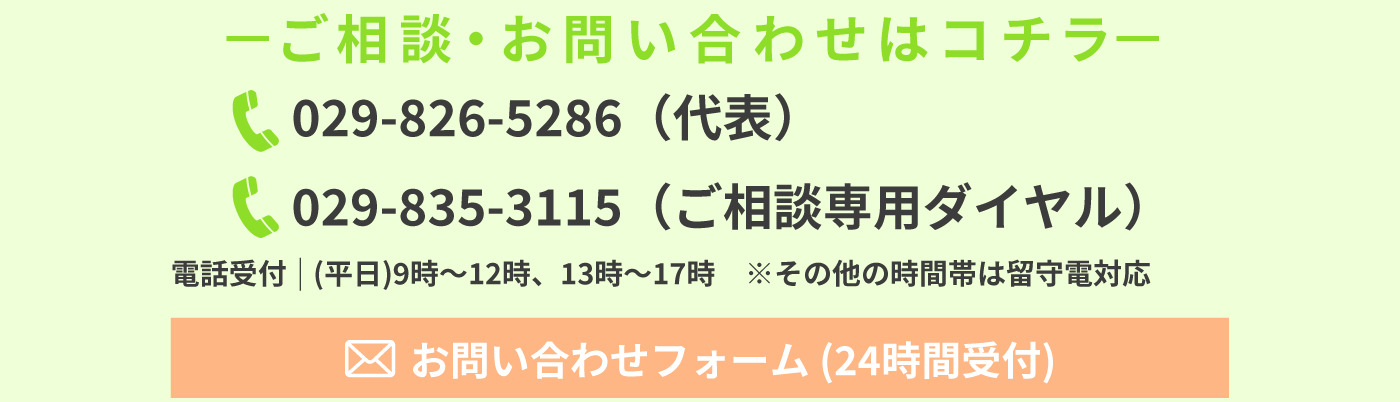Author Archive
メディア出演情報
髙田知己法律事務所です。
本日平成27年12月17日付茨城新聞朝刊22面(民法の再婚禁止期間に関する規定を違憲とした最高裁判決および夫婦別姓禁止を合憲とした最高裁判決に関するニュース)について、当事務所代表弁護士髙田知己のコメントが掲載されました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
労災事件について
弁護士の大和田です。今日は労災事件についてお話しします。
仕事中に怪我をしてしまったというのが労災事件の典型です。
労災事件の場合,労災保険給付を受ける手続を進めることになりますが,労災保険給付だけでは賠償されない損害もあります。
その場合には,使用者に対して,賠償請求していくことになりますが,賠償額で折り合いがつかない時などは,訴訟提起なども視野に入れる必要があり,弁護士の手助けが必要になってくると思います。
当事務所では,労災事件も扱っておりますので,お気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
倒産処理実務に関する研修会
弁護士の若林です。
先日、全国倒産処理弁護士ネットワーク主催の「関東地区第31回研修会」が甲府で開催されました。
当事務所は、この研修会に積極的に参加しております。
今回も、「11時ちょうどのあづさ13号」で行って参りました。
当日は天気がとても良かったため、車窓からは富士山が綺麗に見えました。
さて、肝心の研修はというと、
前半は裁判所による倒産事件処理の実情と中小企業再生支援協議会による活動報告、
後半は管財人業務をテーマとしたパネルディスカッション、という二本立てでした。
倒産処理実務では、不動産売買や企業の在庫品処分を扱うことがありますが、
ここにその地域ならではの特色を見ることができます。
今回は「宝石等の高価品をどう保管し、換価するか」という議論が繰り広げられました。
これは宝飾関係企業が多い山梨ならではの話題だったと思います。
もし、今後、当事務所で宝飾関係企業の業務を扱うことになったときには、今回の話題が活きることでしょう。
次回の第32回研修会は、我が茨城県水戸市で開催されます。
はたして茨城県の倒産処理実務の特色としてどんなものが挙げられるのか・・・
とても興味深いところです。
当事務所は、当然、次回も参加予定です!

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第14回全国大会(福岡)
弁護士の高田です。
全国倒産処理弁護士ネットワーク第14回全国大会(福岡)に参加してきました。今回は全国大会であるため、通常の大会とは異なり、常務理事・理事の人事承認や会則の改正などの議題が検討されました。また、次回の第15回全国大会は2016年10月1日(土)札幌市が予定されています。
シンポジウムについては福岡地方裁判所の民事第4部総括判事からの福岡地裁における倒産事件処理に関する特別講演が行われました。
また、東京大学大学院法学政治学研究科の沖野眞已先生の基調講演が行われました。民法の基本から紐とかれる破産法の解釈はたいへん興味深いものがありました。
福岡弁護士会の有志が今回の大会にあわせて非常に充実したアンケートを行いその結果の発表も行われました。破産処理に関して破産財団の管理又は換価が困難な案件を経験した弁護士に対するアンケート調査の結果報告です。全国の弁護士を対象としたアンケート調査を実施し(回答者総数184名)調査された結果です。大変参考になる具体例が多く記載されていました。
その後のパネルディスカッションは「破産事件における管理・換価困難案件の処理を巡る諸問題~特に法人破産事件について考える~」でした。弁護士、裁判官、研究者での視点の違いが勉強になります。
今後とも研鑽を重ねなければならないと感じる一日となりました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用について
弁護士の小沼です。
弁護士事務所(法律事務所)は,なかなかに敷居が高い場所かと思います。そこで,その敷居がいくらかでも下がるよう,弁護士費用についてご説明いたします。
1 法律相談
当事務所の場合であれば,「法律相談料」は30分につき5,400円(消費税8%込)となります。なお,東日本大震災時に茨城県内の一部地域にお住まいだった方は,30分の無料相談が可能な場合があります。
また,弁護士に相談したからといって,すぐに事件処理を依頼したことにはなりません。相談とは別に,事件処理を依頼する契約を結ばない限り,後述の費用は発生しません。つまり,相談のみでも可能です。
2 弁護士に事件処理を依頼する場合
弁護士に事件処理を依頼した場合には,以下の各費用が発生することがあります。
「着手金」とは,弁護士に事件処理を依頼した場合にかかる費用です。事件処理がうまくいったかどうかにかかわらず,発生します。
「報酬金」とは,弁護士の事件処理が一部でも成功した場合に発生する費用です。一般的には,請求した側であれば獲得した金額に応じて,請求を受けた側であれば減額した金額に応じて発生します。
「実費」とは,弁護士が事件処理に際し,切手や印紙を使用したり,登記事項証明書を取得したりする場合等,実際にかかった費用のことです。
3 まとめ
弁護士に相談する場合には「法律相談料」が,その後,事件処理を依頼すれば「着手金」が,事件処理がうまくいけば「報酬金」が,弁護士が事件処理に切手や印紙等を使用すれば「実費」がかかることになります。
現在,弁護士報酬は自由化されており,金額に決まりはありません。もっとも,多くの事務所では「旧日本弁護士連合会報酬等基準」をもとに弁護士報酬が決めているようです。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
時効について
弁護士の北村です。
日常会話でも「この話はもう時効だから」などと言われることがありますが、私たち法律実務家にとって、時効はとてもよく出くわす問題です。
法律上、時効にもいくつかのカテゴリーがあります。
1つは、消滅時効と言われるものです。一定期間、権利が行使されないまま経過することで、債権(債務)が消滅します。
例えば、ずっと昔に借り入れをしたものの、支払いが滞ったまま10年以上経過した場合、消滅時効を主張できる可能性があります。
ただし、時効は、当事者が主張(援用)しない限り、その効果は発生しません。例えば、忘れた頃に突然債権者から連絡が来て、言われるがままに手持ちの金額を支払ってしまったような場合、後からはたと気づいて時効援用することはできなくなってしまいます。また逆に、過払い金が発生していても、取引から時間が経ち過ぎてしまうと、消滅時効によって請求できる金額が減ってしまう可能性があります。
そうなってしまっては天地の差ですので、思い当たる方はお早目に弁護士に相談してみることをお勧めします。
2つ目は、取得時効と言われるものです。例えば、親の代やそれ以前から自分の土地だと思って使っていたのに、実は他人の土地であったことが分かった場合(このようなケースは、隣地との境界も絡んで、案外多いものです)、取得時効が成立していれば、登記を現況に一致させることができる可能性があります。
調査・交渉・訴訟対応など、複雑な対応が必要な場合も少なくありませんので、一度専門家のアドバイスを聞いてみてもよいかもしれません。
これら以外でも、法律上様々な期間の制限(厳密には時効とは異なるものも含む)が存在します。期間の経過について法律はとてもシビアですので、相談は早め早めを心掛けたいですね。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
少年事件について
今日は少年事件についてお話しします。
少年が犯罪をした疑いがある場合,全て家庭裁判所に送致されます。
大人の事件であれば,起訴されれば必ず国選で弁護人がつきますが,少年事件の場合は,裁判官の職権に委ねられています。
ですから,少年が家庭裁判所に送致されても,国選で付添人(少年事件の場合,家庭裁判所送致後に少年のために活動する弁護士を付添人といいます。)が活動できるとは限りません。
しかし,国選で付添人がつかない場合でも,弁護士の手助けが必要な事件はたくさんあります。
示談交渉をまとめたり,環境を整備し,それを裁判官に分かってもらうためには,弁護士の手助けが必要不可欠です。
当事務所では,少年事件を積極的に受任しております。
お子様が逮捕されたなど,少年の刑事事件でお困りのことがありましたら,当事務所までご連絡下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
登記と現状が一致しない場合
弁護士の若林です。
皆さんは、ご自身が所有する不動産の登記簿を見たことがありますか?
登記簿には不動産に関する様々な情報が記載されています。例えば、登記簿の「甲区欄」を見れば、「誰が」「いつ」「どのような原因」でその不動産を取得したのか、その不動産の「歴史」を知ることができます。
ちなみに、登記簿を取得できるのは、法務局です。
通常、不動産に権利変動があった場合には、法務局に申請し、変動の内容を登記簿に反映してもらいます。そのため、登記簿の記載内容と現実の権利関係は一致しています。
しかし、時々、登記簿上の権利関係と現実の権利関係とが一致しないことがあります。不一致の原因には様々考えられますが、権利関係が一致していないと、不動産の売却や処分、担保権設定等ができず、不動産の活用に支障を来してしまいます。この場合、登記簿と現状の不一致を修正する手続きを取らなければなりませんが、不一致のまま長期間放置していた場合、当事者の行方が分からない、相続等で関係者が複数人いる等の事情が生じてしまい、対応に非常に苦慮することとなります。
場合によっては、訴訟等で不一致状態を解消せざるを得ないこともあります。
訴訟対応は私達弁護士の得意分野です。
もし、ご自身の不動産登記簿を見て、「権利関係が不一致の状態だ!」なんてことがありましたら、弁護士に相談するという選択肢も忘れないでくださいね。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
茨城の弁護士 相続の話 3
弁護士の高田です。前回に続いて、相続について考えてみたいと思います。
相続は、多くの人にとって、何度か発生することのある法律上の問題です。この際、不動産や預貯金など、積極的な財産が相続されるだけなら良いのですが、借金や義務などが相続されることもあり、注意して当たる必要のある事柄です。
相続は、民法上、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認の三つの種類があります。
今日は、③限定承認について、説明したいと思います。
限定承認とは、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです(民法第922条)。
条文上の表現だとわかりにくいですが、つまり、限定承認をすると、相続で取得する財産で被相続人の借金等をすべて支払って残りがあればこれを相続できるが、相続で取得する財産を超えて借金等が残ってしまえば、これについては責任を負わなくて良いということです。
被相続人と同居している場合であれば、被相続人がどの程度の財産を持っていて、借金がどの程度あるかわかることが多いでしょうから、単純相続や相続放棄で対応ができると思います。しかし、被相続人と生前に疎遠である場合などは、被相続人がどの程度の財産や債務を負っているかわからない場合が多いでしょう。このような場合には、考えても良い制度の一つだと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
逮捕された場合について
弁護士の小沼です。あまり馴染みのない手続きかと思いますので,
逮捕された場合やその後の流れについて,ご説明させていただきます。
「逮捕」
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある人物(被疑者)は,警察等により,
逮捕されることがあります。
逮捕されてからの身柄拘束期間は最大72時間です。その間に勾留請求がされると,
被疑者勾留という段階に移り,逮捕に引き続いて身柄拘束が継続されます。
「被疑者勾留」
被疑者勾留の期間は10日間で,多くの場合,更に10日間延長されます(計20日間)。
この期間内に検察官は起訴(裁判)をするかどうかの決定をします。
「被告人勾留」
起訴されると呼び名が被疑者から被告人に変わります。
被告人勾留の期間は2ヶ月間であり,1ヶ月ごとに更新されることがあります。
被告人勾留の段階には,保釈という身柄拘束を解放する制度が存在します。
なお,裁判は通常,起訴されてから1ヶ月~2ヶ月ほどで開かれます。
手続きの各段階に応じて様々な弁護活動があります。
取調べを受けるに際してのアドバイスや,被害者との示談交渉をまとめることにより,
起訴をされないようにするなどの活動も行ないます。
万が一,ご友人やご家族が逮捕されるという事態が生じた場合には,当事務所までぜひご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。