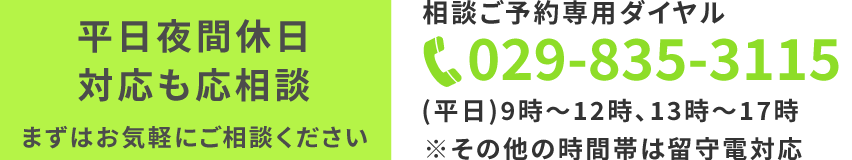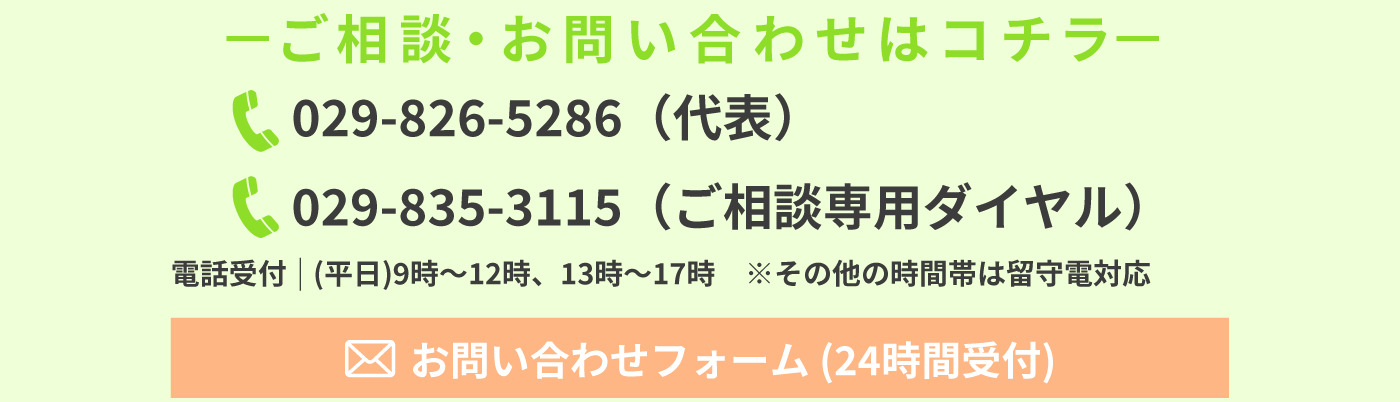Author Archive
ゴールデンウィーク期間中の休業日のご案内
ゴールデンウィーク中の営業は下記の通りになります。
4月29日(金)~5月 1日(日)休業
5月 2日(月)通常営業
5月 3日(火)~5月 5日(木)休業
5月 6日(金)通常営業
5月 7日(土) 5月 8日(日)休業
何卒宜しくお願い申し上げます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
会社の借金問題 解決事例のご紹介など
今回は会社の借金問題の対応について、ご説明したいと思います。
コロナ渦の影響で業績が悪化し、会社の存続を含めてご相談いただくことが多くなりました。
経営者としては会社の存続を第一に考えるのは当然のことです。
しかし、会社の財務状態から破産も選択肢に入れていれなければならいこともございます。そのような場合は、まずは、法人破産の申立ての経験のある弁護士に相談してみて下さい。弁護士も無理に破産を勧めることはありませんし、法人破産の申立て経験のある弁護士の視点からのアドバイスは今後の方針の参考になるのは間違いありません。
当事務所は下記のとおり、法人破産申立ての実績が豊富ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
また、実際に、法人破産の申立てを依頼する場合には、実績に加えてマンパワーも必要不可欠です。会社の破産の場合には、短期間のうちに破産申立てすることが求められますので、マンパワーのある事務所でなければ円滑な対応ができなおそれがあります。当事務所は弁護士5名、事務員8名と人員豊富ですので、ご依頼の際もご安心下さい。
記
解決事例のご紹介
ほんの一部ですが、解決に至った事業者の借金問題についてご紹介させていただきます。
1 会社(製造業) 債務額 4億0600万円
取締役 債務額 6800万円
2 会社(製造業) 債務額 2億6000万円
取締役 債務額 2億3000万円
3 会社(販売業) 債務額 1億5000万円
取締役 債務額 1億円
4 会社(建築業) 債務額 4700万円
取締役 債務額 2900万円
5 会社(人材派遣) 債務額 8400万円
取締役 債務額 3400万円
6 会社(商社) 債務額 3600万円
取締役 債務額 3000万円
7 会社(飲食業) 債務額 3700万円
代表者 債務額 3200万円
8 会社(製造販売業) 債務額 1700万円
代表者 債務額 5300万円
9 会社(飲食業) 債務額 1200万円
債務額 1400万円
10 個人事業主(フランチャイズ店オーナー) 2200万円
11 個人事業主(販売業3店舗オーナー) 5100万円

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
茨城県土浦の刑事弁護 私選が有効な場合
本日は私選弁護人の選任が有効な場合についてご紹介したいと思います。
警察官に逮捕された場合、72時間以内に10日間勾留されるか決まります。
国選弁護人が選任されるのは10日間の勾留が決まってからになりますので、逮捕段階から弁護を受けたい場合は私選弁護人を選任する必要があります。
最大で72時間程度なら弁護を受けられなくてもいい、勾留が決まってから国選弁護人に頼めばいいと思われるかもしれません。
しかし、勾留を避けたいのであれば私選弁護人の選任が非常に有効です。
私選弁護人であれば逮捕段階から、勾留されないように検察や裁判所に意見を述べることができます。
その結果、検察官が勾留を請求しなかったり、検察官が請求したとしても裁判所が勾留を認めないということもあります。
一度勾留が認められてしまうとそれを後から覆すのは大変です。ですので、勾留を避けたいのであれば私選弁護人を選任をご検討下さい。
当事務所では、勾留請求当日にご家族から依頼を受け、直ちに接見して事情を把握した上で意見書を裁判所に提出し、勾留請求を却下できたことがありました。ご依頼から8時間ほどで警察署から出ることができたので依頼者の方にも満足いただけました。
このように私選弁護人の選任が有効なケースもありますので、ご家族が逮捕された場合にはお早目にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
年末年始の休業日のご案内
誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。
【最終営業時間】
令和3年12月28日(火)12時まで
【年末年始休業期間】
令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)
令和4年1月6日(木)より通常営業となります。
休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
死亡事故における慰謝料について
交通事故により被害者の方が死亡した場合には,死亡したことについての慰謝料が発生します。今回は,この死亡慰謝料についてご説明します。
死亡慰謝料とは,被害者の方が死亡したことによる精神的損害のことです。亡くなられた方の生前の立場により,その額が異なってきます。
損害賠償額算定基準(2021年版)によりますと,次のとおりです。
①一家の支柱 2800万円
②母親・配偶者 2500万円
③その他 2000~2500万円
近親者の方の慰謝料を含む額ではありますが,あくまで目安であり,相手方となる保険会社が前述の額を必ず支払うというものではないことにご注意ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第19回目「改正相続法の概要―相続の効力等に関する見直し―」
弁護士の若林です。
今回は、相続の効力等に関する見直しについて説明します。
例えば、父親Aが亡くなり、相続人が長男Xと次男Yの2人であったとします。
Aの相続財産としては自宅不動産しかなく、かつ、Aは生前「自宅は長男Xに相続させる」との遺言書を作成していました。
Xが遺言書に基づいて自宅不動産の登記を自分名義に変更する前に、Yが法定相続分で登記手続きをしてしまい、その後第三者Sに自分の持ち分(1/2)を譲渡、登記をしてしまったとします。
つまり、本来Xの単独所有として登記されるべきところが、XとSが2分の1ずつ共有する内容で登記されている状態です。
この場合、改正前は、Xは登記を備えたSに対して、自宅不動産の所有権(全部)を主張することができました。
他方、Aが遺言書を作成しておらず、XとYが話し合い、自宅不動産をXが単独で相続する遺産分割協議をしていた場合で、その後YがSに持ち分(1/2)を譲渡、移転登記してしまった場合はどうでしょうか。
この場合、改正前は、Xは登記を備えていないため、YからSに対して自宅不動産の所有権(全部)を主張することができませんでした。
このように、法改正前、Xが登記を備えたSに対して所有権(全部)を主張できるかどうかは、AのXに相続させる旨の遺言の有無によって変わります。
ですが、通常、第三者は亡くなった人がどのような内容の遺言書を残していたのかを知ることは困難です。
それなのに、遺言の有無・内容によって権利関係が変わってしまうのは、第三者の利益を害することになりますし、登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれもあります。
そこで、改正法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとしました。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
死亡事故における損害について
今回は,交通事故により被害者が死亡した場合,遺族が請求することになる主な損害についてご説明します。
1 死亡慰謝料
被害者が死亡した場合の精神的損害です。近親者の慰謝料を含む場合,生前の立場により金額が異なります。
2 逸失利益
働いていれば得られたであろう収入に関する損害です。生活費分は差し引かれます。
3 葬儀費用
一定額まで認められます。必ずしも全額が認められるわけではありません。
各損害の詳細については次回以降にご説明させていただきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士の夏休み
弁護士の北村です。
働き方の多様性が叫ばれる昨今,弁護士の勤務形態も多様化していますが,こと茨城県では伝統的な個人事業主の形態を取る弁護士が多いように思います。
そんな弁護士たちがどんな夏休みを過ごすかは,まさに人それぞれです。長期休暇を取って旅行に出る人もいると聞きます。逆に,仕事の整理に勤しむ弁護士もいると聞きます。
因みに当事務所では,お盆を含めて決まった夏休み期間はなく,暦通りの営業です。各弁護士が各々のタイミングで休暇を取得しています。
私自身は,例年ならば連休を取って普段行けない国内遠方への旅行に行っていましたが,昨年に引き続き今年も難しそうですね。
新型コロナウイルスとこれに伴う様々な法律問題が早期に収束しますように。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故 物損 買替費用
今日は、交通事故で車が破損し買替える場合に、買替費用も損害として認められるかについてご説明します。
買替費用でも損害として認められるものは、以下のものがあります。
・車庫証明費用
・検査登録法定費用
・車検証名法定費用
・納車費用
・検査登録手続代行費用
・車庫証明手続代行費用
・リサイクル預託金
限定的に損害として認められるもの
・自動車取得税(2019年10月1日以降は自動車税環境性能割)は、被害車両と同車種、同型式の車両を再調達した場合における自動車取得税相当額は認められます。
・消費税も同様です。
認められないもの
・自動車税
・自賠責保険料
これらは還付制度があるので認められません。
このように、買替費用でも認められるもの、認められないものがあります。
損害の上乗せができるとしても数万円~数十万円ほどになることが多いですが、弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。
当事務所では買替費用も認めてもらい、賠償額の上乗せができた事例も多数ありますので、買替費用を相手保険会社が認めてくれないなど、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」
弁護士の若林です。
今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。
遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。
相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。
遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。
たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。
共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。
このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)
また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。