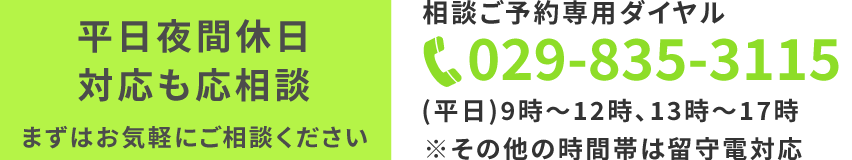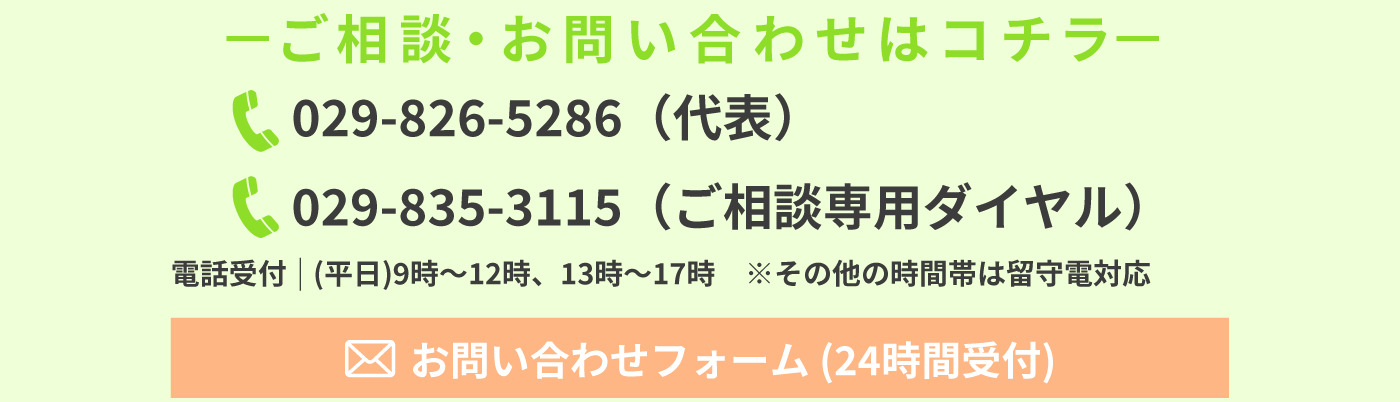Author Archive
破産や個人再生をしたいと思ったときの弁護士の探し方
あなたが、借金でお困りの時には弁護士と相談することをお勧めします。
弁護士が、あなたのお話を聞いて破産や個人再生など、あなたに最適な解決方法を教えてくれると思います。
では、どのような弁護士に相談すべきでしょうか。
債務の問題が得意な弁護士を見つけましょう
まず、債務整理について詳しい弁護士を選ぶ必要があります。医師とは異なり、弁護士は必ずしも専門分野を持っているわけではありません。
しかし、破産をほとんどやったことがない弁護士さんも少なくはありません。特に個人再生はさらに特殊性が強いので精通した弁護士を選ぶ必要があります。
では、そのような債務の問題に詳しい弁護士をどのように探せばよいのでしょうか。
まず、初回の相談時に聞いてみるというのも良い方法だと思います。ただ、直接聞くのはなかなか難しいという場合もあると思います。そのような場合には、その法律事務所のホームページを見ることも良い判断材料になると思います。ホームページ上での債務の問題について取り扱いが大きい事務所であれば、債務の問題について強い事務所である可能性は高いと思います。
地元の弁護士がお勧めです
破産や個人再生の場合には、その人に合わせた一番良い形で手続きを進めるためには何回も法律事務所に足を運び面談を重ねる必要があります。そのため、ご相談者の方のご自宅の近くやご相談者が通いやすい場所にある法律事務所を選択することが大切です。また、破産や個人再生の手続きはそれぞれの地域の裁判所ごとに異なる取り扱いをしている場合もあります。そのため、相談者の住んでいるところに近い弁護士であれば地元の裁判所の取り扱いにも精通していることが多いでしょう。このようなことも考慮にいれて弁護士を選ぶと良いと思います。
話のしやすい弁護士を見つけましょう
一番大切なことは、相談者の方と弁護士との相性があると思います。債務の問題は無料相談をしている法律事務所も多いので、複数の弁護士と相談の上決めても良いと思います。
あなたの新しいスタートを祈念しています!

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。
コロナ禍吹き荒れる毎日ですが、当事務所でも手指消毒、検温のご協力、消毒の徹底などを行い通常通り業務を行っています。
令和三年もよろしくお願いします。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故と後遺障害認定について。
弁護士の北村です。
髙田知己法律事務所では,開所以来交通事故案件に特に力を入れており,これまでに数多くの案件を解決してきました。
交通事故案件で大きなポイントとなるのは,後遺障害認定が下りるか否かです。後遺障害認定が下りれば,等級に応じた後遺障害慰謝料や,年収をベースに算出される後遺障害逸失利益を請求できることになりますが,非該当であればそれらの請求はできません。
特に見通しが難しいのは,いわゆるむち打ち症,すなわち他覚所見のない神経症状において,後遺障害(主に14級)が認定されるか否かです。私自身もこれまで多くの案件を取り扱ってきましたが,事前予測と逆の結果(いい意味でも悪い意味でも)となることが少なくない印象です。
後遺障害認定が下りるか否かお悩みの方は,ぜひご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が,事案に応じたアドバイスを行います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
2020年 交通事故
弁護士の大和田です。
本年も交通事故のご依頼を多数いただき、誠に有難うございました。
今回は今年担当した交通事故案件の解決事例の一部をご紹介したいと思います。
14級案件
・事前提示から約220万円増額(提示額の2倍以上)
・事前提示から約130万円増額
等級なし
・事前提示から約70万円増額(提示額の10倍)
などがあります。
このように事案によっては、保険会社の事前提示額から大幅に賠償額が上がるものもあります。
保険会社の提示金額がきても、一般の方では妥当なのか分からないということは多々あると思います。
そんな時は弁護士に一度ご相談いただければ、そのまま示談するのがよいのか、弁護士に依頼した方がよいのか見えてくると思います。
当事務所では、交通事故の被害者相談は初回無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」
弁護士の若林です。
今回は一部分割について説明していきます。
遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。
改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。
そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。
民法第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
職務上請求について。
弁護士の北村です。
今日は,職務上請求についてお話をしようと思います。
弁護士が相手方に対してアクションを起こしていく場合,裁判手続にせよ,任意の交渉にせよ,相手方の所在が判明していることが第一関門といえます。
しかし,依頼者ご本人は相手方の細かい住所を把握していない場合も少なくありません。
このような場面を想定して,弁護士等の有資格者について,住民票および戸籍等の職務上請求という制度が認められています(住民基本台帳法第12条の3第2項,戸籍法第10条の2第3項~第5項)。
請求の要件は法律上きっちり定められており,不正請求を防ぐため,日本弁護士連合会の統一書式によって請求することとなっています。また,取得した住民票,戸籍等を請求の目的以外に使用することは固く禁じられています。
また,住民票,戸籍等の調査そのもののご依頼をお受けすることはできません。あくまでも,相手方に何らかの請求等をしていくご依頼を遂行するために必要な限度で認められた請求,ということになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士会照会制度について
みなさん、弁護士会照会制度というのをご存じでしょうか。弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所または公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることを申し出ることます(弁護士法23条の2)。弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をその使命としています(同法1条)。弁護士が、真実発見のための資料を収集することは、弁護士の使命を実現するためにとても大切なことです。弁護士会照会制度は、必要な事実の調査及び証拠の発見収集のための手段として認められています。
もちろん、この制度を利用して回答を得た弁護士は、その回答内容について厳重に管理しなければなりません。理由なく第三者に知らせないことももちろんです。また、弁護士は、紹介により得られた回答を、目的外に使用してはならない義務を負います。
我々弁護士は、この照会制度を利用して様々な情報を取得します。具体的には、判決確定後の相手方の預貯金口座の有無や所在、交通事故における実況見分調書や物件事故報告書など様々な場合があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
最近のトレンド。
弁護士の北村です。
すっかり冷え込みが厳しくなり,木々も色付いてきた今日この頃ですね。
さて,私たち髙田知己法律事務所は,土浦市をはじめ,茨城県南地域の皆様のよき相談相手として,幅広い法律問題について相談をお受けしています。
とはいえ,いつでも全ての分野のご相談予約があるわけでもなく,その時その時でトレンドめいたものがある気がしています。
あくまで私個人の肌感覚ですが,ここ1,2ヶ月くらいは,交通事故と離婚・男女問題の2分野が特にご相談が多かったように思います。
交通事故に関しては,特設サイトhttps://ibaraki-jikobengoshi.com/も開設しており,当事務所が特に力を入れている分野です。これまで数多くの案件で,示談金額の増額などの解決を実現してきました。
離婚・男女問題に関しては,年末が近づいてきたことも関係しているのでしょうか。こちらも,交渉・調停・裁判の各ステップにおいて,数多くの解決実績があります。
交通事故や離婚・男女問題以外にも,借金の問題(個人および事業者),遺言・相続,労働問題・残業代(労働者側),刑事事件その他,幅広く法律相談をお受けしており,法律専門家の立場からアドバイスを行っております。
一人で悩まずに,まずはご相談ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
2020年 過払金
今日は今年も残り2か月を切りましたので、本年の過払金請求の状況についてお話致します。
過払金は年々減少傾向にあると言われていますが、当事務所では本年も多くの過払金請求のご相談、ご依頼をお受けしました。
請求金額も少額なものから600万円を超えるものまで様々にありました。
まだまだ過払請求案件はあるという印象です。
もし、長く返済を続けている借入などがあれば、一度弁護士などの専門家にご相談いただくとよいと思います。
過払金の事務所選びの際に一つ気を付けた方がよいのは、必要に応じて裁判まで行う事務所かどうかだと思います。時間は掛かってしまいますが、裁判をすることによって過払金が増額する可能性があります。
今年は裁判前は170万円程度の提示だったものが、訴訟提起後には300万円を超える和解が成立したというほぼ倍増した案件もありました。
もちろんすべての案件で裁判をすればよいというわけではありません。依頼者様が早期に過払金を得たいという場合や、裁判前の提示額が合理的な場合などは、裁判までせずに和解するのも選択肢の一つです。
ただ先ほどの例にありますように、裁判することを念頭に置いていないと、過払金の回収金額が大きく下がってしまう可能性がありますので、裁判まで念頭においた事務所に相談されるのがよいと思います。
当事務所はもちろん必要に応じて裁判まで行いますので、安心してご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故における後遺障害の認定申請について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に,後遺障害の認定申請をする方法についてご説明します。
1 認定申請の流れ
①後遺障害診断書の作成
症状が固定した段階で,医師により後遺症が残ると診断された場合,医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
②事前認定と被害者請求
加害者側の任意保険に後遺障害の認定申請を任せる方法(事前認定)と,被害者自身あるいは依頼した弁護士により認定申請を行う方法(被害者請求)があります。
③認定
損害保険料率算出機構が公正な立場で調査したうえで,認定結果が出されます。認定結果に不満がある場合には,異議申立を行うことも可能です。
2 まとめ
一度認定されると,その認定結果を覆すことはかなり難しくなります。異議申立を行なわなくても済むよう,最初から丁寧に後遺障害の認定申請を行うことが望まれます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。