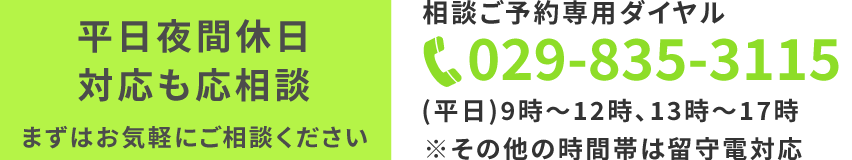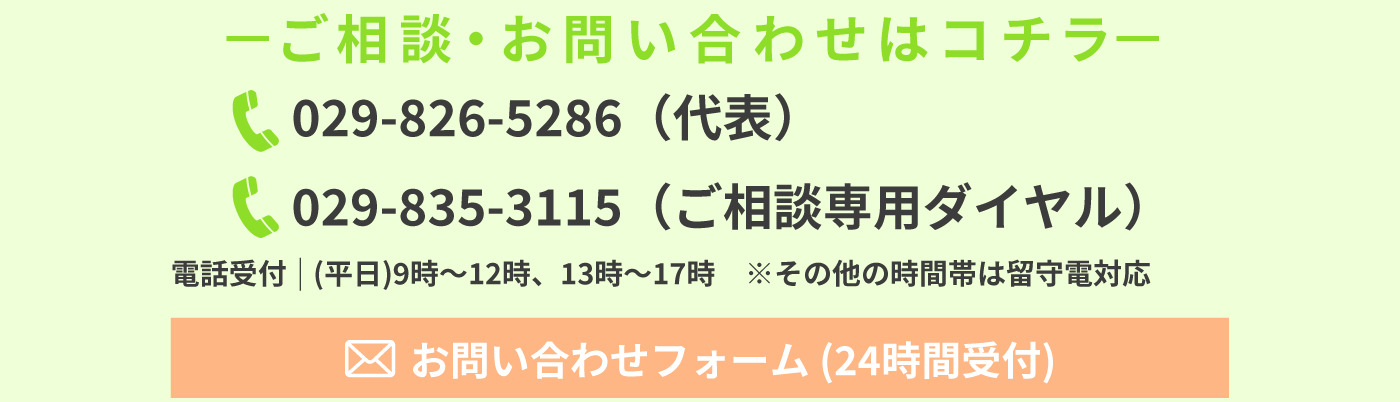Author Archive
令和2年スタート
弁護士の北村です。
新元号になって最初の年明けとなりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて,一般企業や学校などでは4月が入社や入学の季節ですが,弁護士業界では,12月中旬頃と1月1日が最も伝統的かつポピュラーな新規登録の時期となっています。その理由は,法曹養成課程である司法修習の修了試験結果発表が12月中旬頃に行われるためです。かく言う私も,昨年12月に弁護士登録から満6年となりました。
時事ネタになりますが,最近日本の法曹や司法制度に対する世間の風が厳しくなっているよう思います。国内外から様々な変革を求められている令和の今,法律専門家としてのスキルと倫理観,そして人間としてのマインドをさらに磨いていかなければ,と身を引き締めています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
逮捕されそうになったら
弁護士の大和田です。
今回は刑事事件における私選弁護人のメリット、デメリットについて解説致します。
弁護人には、自ら又は家族などが費用を負担して選任する私選弁護人と国選弁護人があります。
メリット1 いつでも選任できる
国選弁護人は、逮捕後に勾留された段階から選任が可能となります。これに対し、私選弁護人はいつでも選任することができます。逮捕されただけでは国選弁護人を選任することはできませんので、逮捕段階あるいはその逮捕される前から選任できるところに私選弁護人のメリットがあります。例えば、傷害事件など被害者のいる事件において、逮捕段階で私選弁護人を選任し、被害者と示談をして勾留(最長で20日間)を回避するというような対応も考えられます。
メリット2 自分で選べる
国選弁護人は選ぶことはできませんが、私選弁護人は選ぶことができます。国選弁護人と気が合わないという場合でも、違う国選弁護人を選任してもらうということは基本的にできません。弁護人にも様々なタイプがあり、刑事事件の経験も様々ですから、自分にあった弁護人を選ぶことができるというのはことのほか大きなメリットといえるでしょう。
メリット3 複数選任できる
国選弁護人の場合、裁判所の許可がなければ一人の弁護人で対応せざるを得ません。これに対し、私選弁護人であれば、自らの意思で複数の弁護人を選任可能です。当事務所では弁護士が6名おりますので、希望に合わせて複数の弁護人を選任できますし、複数選任したとしても費用は変わりません。刑事事件も様々な観点から考える必要がありますので、複数選任ができる点もメリットといえるでしょう。
デメリット 費用がかかる
これに対し、私選弁護人のデメリットは費用がかかることが挙げられます。経済的な余裕がない場合には、国選弁護人の選任を待つことになるでしょう。
小括
以上のように、経済的な負担があるということ以外は、私選弁護人を選任するメリットは大きいといえます。刑事事件でお困りの際には、お気軽にお問合せ下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
臨時休業のお知らせ 11月27日水曜日
髙田知己法律事務所の髙田知己です。
令和元年11月27日水曜日ですが、研修のため臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
借金 債務 でお困りの方へ
弁護士の髙田 知己です。
借金の返済のために、他から借りて、その借りたお金で返済をしている方はいらっしゃいませんか。借金で返済をはじめてしまうと借金の額はあっという間に膨らんでしまいます。そのため、借金による返済を続けると、借金の額が増えてしまい返済できなくなってしまうかもしれません。その前に、弁護士に相談してみることを考えてみてください。あなたと一緒に月々の返済可能な金額と、返済計画を考えてみたいと思っています。
返済できなくなってしまっている方の場合には、いわゆる破産手続きをする必要があります。返済できるかどうかは、3年もしくは4年で返済できるかどうかが、ひとつの目安といわれています。生活費などでの借り入れでこの期間に返済ができない方も弁護士への相談をお勧めします。
当事務所は、借金の問題にも積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談いただければと考えています。お電話いただいて予約をお願いします。相談ダイヤルは
029-835-3115
になります。
借金の問題の場合には、お急ぎの相談も少なくないと思います。できる限り対応したいと考えていますので、お急ぎの方は、予約時にその旨もお伝えいただけるようお願いします。
ご相談をお待ちしております。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第11回目「改正相続法の概要ー配偶者の居住を保護するための方策(2)-」
弁護士の若林です。
今回は、①配偶者の居住を保護するための方策のうち、配偶者短期居住権について説明します。
配偶者短期居住権が新設された趣旨は配偶者居住権と重なりますが、主に、被相続人が居住建物を第三者に遺贈してしまった場合や反対の意思を表示していた場合でも、最低6カ月間は配偶者の居住権を保護するというものです。
具体的な条文は以下のとおりです。
民法第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で居住する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合
第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 略
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者は、①被相続人の配偶者であること、及び②相続開始の時に被相続人が所有する建物に無償で居住していたことの要件を満たせば、配偶者短期居住権を法律上当然に取得することができます。
配偶者短期居住権については、遺産分割の際に具体的相続分からその価値を控除する必要はありません。
配偶者短期居住権は、①存続期間満了、②居住建物取得者による消滅請求がされた場合、③配偶者が配偶者居住権を取得した場合、④配偶者死亡、⑤居住建物が全部滅失した時等に消滅し、居住建物を居住建物取得者に返還することになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
裁判IT化について
弁護士の北村です。
社会のIT化,デジタル化が進んで久しいですが,裁判手続においては2019年現在でも濃いアナログ色が残っています。
裁判期日には,基本的には裁判所に出頭する必要があり,電話会議システムやテレビ会議システムが活用される場合は限定的です(弁護士としても,電話会議より直接出頭の方が優れているような感覚が染みついています)。
提出書類は,原本および副本ないし写しを,裁判所に持参もしくは郵送・FAXで提出するよりありません。また,基本的には書面への押印が必要です。手続に必要な収入印紙や郵券も,基本的には物納です(手続によっては電子納付ができますが,限定的です)。事件記録の管理をデジタル化している弁護士もかなり少数だと思います。社会で広まっているオンライン化,ペーパーレス化,電子署名化といったところは,まだまだ浸透していません(もちろん,法律上の権利義務にかかわるというセンシティブな世界であるため,紙媒体の原本が重視されることにも相応の理由があるわけですが)。
とはいえ,裁判手続IT化に向け,時代の要請は高まっているようです。現在,民事裁判手続における書面や証拠のオンライン提出システムの導入や,手続のウェブ会議システムの導入の方向で議論が進んでいます。具体的な制度設計については,これから明らかにされることと思います。
法律も手続も大変革の最中にあるといえますが,髙田知己法律事務所は,社会の最前線におけるニーズに応え続ける法律事務所を目指してまいります。そのためには,今後とも最新情報のフォローアップを続けていかなければ,ですね。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故における損害について
弁護士の小沼です。
今回は,交通事故の被害者になってしまった場合に,相手方に対して,どんな損害を賠償請求していくことになるかについてご説明します。なお,賠償が認められるのは相手方に過失が認められる部分(相手方の過失割合部分)に限られます。
1 車が壊れてしまった
「修理費用」「代車費用」について請求することができます。この他に「廃車手続費用」「評価損」等が請求できる場合があります。
2 怪我をした
「治療費」「通院交通費」「傷害慰謝料」「休業損害」等を請求することができます。後遺障害が存在する場合には「後遺障害慰謝料」「逸失利益」等も請求することになります。
3 死亡した
被害者の相続人から請求することになります。具体的には「死亡慰謝料」「逸失利益」「葬儀費用」等を請求することができます。
今回は,交通事故における損害の概略についてご説明しました。次回以降は,各損害の詳細についてご説明します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
残業代請求 ~労働時間の立証~
弁護士の大和田です。
今回も残業代請求において、問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは、労働時間の立証です。
残業代請求においては、当然のことながら、労働者の方で自分が働いた時間の立証をしなければなりません。
多くの裁判例において、タイムカードなど客観的な記録により時間管理されている場合は、特段の事情のない限り、タイムカード打刻時間をもって実労働時間と推定されています。
もっとも、客観的な証拠が手元にない場合には、それを入手するところから始める必要があります。
会社側が開示に応じてくれればよいですが、それが難しい場合には、弁護士を通じた開示請求、文書送付嘱託、文書提出命令などの手段をとることも考えられます。また、タイムカードなどを破棄されるおそれがある場合には証拠保全の手続きを考える必要があります。
これらの手続きは法的知識が要求されますので、証拠の入手に困っている時などは、弁護士に相談されてみてもよいかと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
相続第10回目「改正相続法の概要ー配偶者の居住権を保護するための方策」
弁護士の若林です。
今回は、改正相続法のうち、①配偶者の居住権を保護するための方策について見ていきます。
現代は「人生100年時代」という言葉が象徴する様に平均寿命が伸びており、従来に比べると相続開始時の配偶者相続人年齢が高齢化しています。そして、高齢の方にとって居住環境の変更は特に大きな負担となるため、相続開始後も住み慣れた住居での生活を希望される方が多いです。
被相続人の財産に配偶者が居住している不動産が含まれている場合、上記希望を叶えるためには、不動産を配偶者が相続する(所有権を取得する)、又は、不動産を相続する相続人と配偶者間で賃貸借契約を締結する内容で遺産分割協議をまとめられれば良いのですが、残念ながら調整がつかないこともあります。
また、不動産を配偶者が取得することになった場合でも、不動産の評価額が高額で配偶者がそれ以外の相続財産(例えば預貯金や現金等)を相続することができず、今後の生活資金に不安が生じることもあります。
このような事態を踏まえ、法改正の結果、以下の内容の条文が設けられました。
民法第1028条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
(以下略)
改正相続法では、配偶者に居住建物の無償使用権限を認める配偶者居住権を新設し、配偶者が居住建物に住み続けることができるようにしました。しかも、配偶者居住権の取得額は居住建物の所有権の取得額よりも低廉であるため、配偶者居住権を取得した上で更にその他の相続財産(現金や預貯金等)を取得しやすくなります。
さらに、次回以降に触れる「持ち戻し免除の意思表示の推定」が及ぶ事案であれば、配偶者の具体的相続分から配偶者居住権の取得額を控除する必要がなくなります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
ライプニッツ係数をご存知ですか(交通事故の賠償請求)
弁護士の髙田知己です。みなさん、ライプニッツ係数をご存知でしょうか。一般の方はあまり聞き覚えのない言葉だと思いますが、弁護士にとって交通事故の賠償請求をするときに重要な概念となります。
ライプニッツ係数とは、将来発生する損害、例えば介護費用や働いて得られるはずだった利益を、今貰う場合に減額することによって調整しようとするものです。具体的に考えてみましょう。まず、10年先に発生する損害である1万円を今請求するという場合を考えてください。もし利息が年に10%であれば、今1万円をもらうと10年後には利息が年間1000円10年で利息と合わせて総額2万円になってしまいます。運用を変えて複利にするとかするとさらに増額も見込めます。このように考えると将来もらえるはずのお金を今請求する場合には、少し少なめにしないといけませんよね。その調整のための計算方法がライプニッツ係数と呼ばれるものになります。
しかし、現在実務上使われているライプニッツ係数は被害者側にとても不利なものと私は考えています。銀行などに預けておけばとても高い金利のついた昭和の時代であればともかく、現在は銀行に預けてもほとんど利息はつきません。
現在のライプニッツ係数はどのようなものか具体的に考えてみます。
最初に10年間継続して発生する損害について考えます。1年間100万円の損害が発生するとした場合には、10年間で合計1000万円の損害が発生しますよね。では、ライプニッツ係数をかけるとどうなるでしょうか。
10年のライプニッツ係数は7.7217になります。なので、この場合には、約770万円となります。
しかし、これがバランスのとれた金額とお感じになるでしょうか。私には、そうは感じられません。
では、50年間損害が継続して発生する場合にはどうでしょうか。同じく年間100万円の損害が発生すると考えると、50年で5000万円の損害が発生します。50年のライプニッツ係数は18.2559です。この場合には、約1800万円となります。これは、バランスを欠くと考えざるを得ない数字ではないでしょうか。
この計算方法は現在定説といっても過言ではなくプロとしてはこれ以外の見解を主張することは著しく困難です。
このライプニッツ係数は、上記のように利息というものがあることを前提に考えていて、現在の係数はこの年利が5%であることを基礎に導かれています。来春の民法改正により民法上の利息が3パーセントになります。そのため、令和2年4月以降の事故においては新しいライプニッツ係数が適用されることになりそうです。
令和元年9月5日

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。